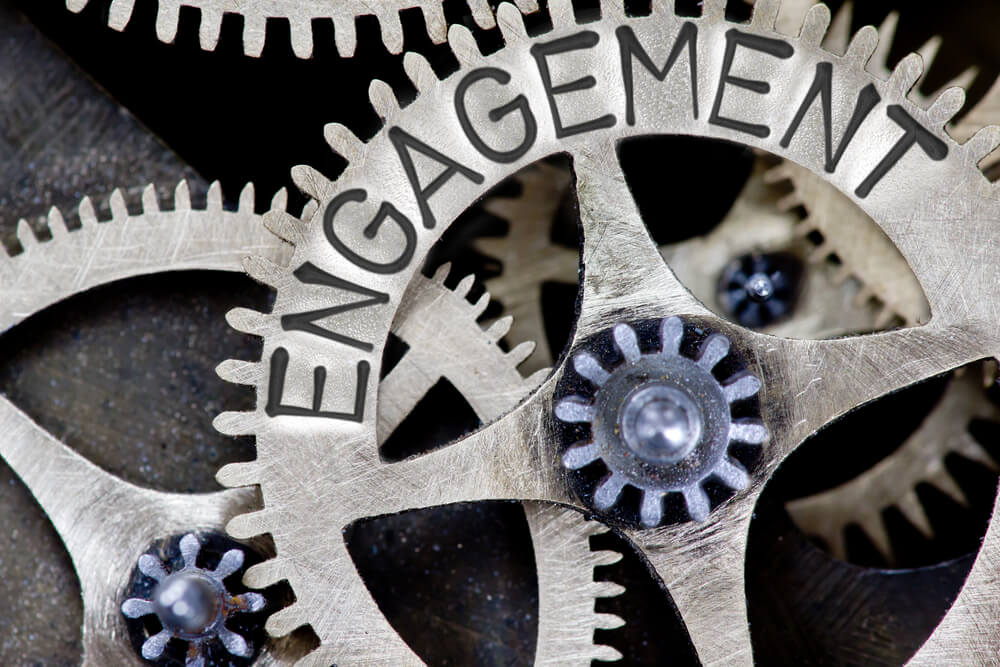近年、日本でも「組織開発(Organization Development)」という概念が注目されています。組織開発とはもともとアメリカで生まれた概念であり、企業風土や社員相互の関係性が、どのように個々の社員や集団のモチベーションに影響を与えるかなどのプロセスを調査し、分析結果にもとづいて組織を改善していくサーベイ・フィードバックの流れをくんでいる施策の一つです。
この記事では、組織開発の代表的な手法について解説します。

目次
組織開発の目的とは何か?
そもそも、組織開発の目的とは何でしょうか?広義で言えば、集団のシナジー効果が高まるような組織風土を醸成し、個々の従業員のモチベーションを高め、企業の生産性を上げていくことだと言えるでしょう。
組織開発というと聞きなれないかもしれませんが、2000年以降多くの日本企業は人事制度を変革し、コーチング、チーム・ビルディング、ファシリテーションなどの組織開発の手法を積極的に取り入れてきました。
ただし、どの施策も個々の社員の能力向上には結びついても、組織全体の活性化にまでは至らなかったのではないでしょうか。
人材開発の目的で取り組んでいる場合は成果といえますが、「人」にフォーカスして組織全体に変化を促す手法に対して、多くの企業がある種の限界を感じてきたことが、近年、組織開発が注目されている理由の一つだといえるでしょう。
行動科学の知見をもとに「個人」ではなく組織としての「個々人の関係性」、「点」ではなく「面」で組織をとらえてアプローチする組織開発という手法に、多くの企業がいま関心を寄せています。
組織開発の基本的な手法について
組織開発にはいろいろなテクニックが用いられますが、組織全体にアプローチする場合は、以下のステップを踏むことが一般的です。
1.目的の決定
2.目的と現状の差の把握
3.課題の設定
4.試験的アプローチ(少数の部門でトライアル)
5.効果の検証・フィードバック
6.成功事例をベースに全社的に実施
組織開発はあくまで手段であり目的ではありません。組織開発を行うにあたっては、まず自社の目的を明確に定めることが重要です。そして、職場の実態を調査し現実をシビアに把握する必要があります。
日本で組織開発の研究を長年続けている南山大学の中村和彦教授は、企業が組織開発を成功させるヒントは『現状でどのような問題が起こっているかを認識すること(問題設定)の方がまずは重要』と述べています。(日本経済新聞、2018年12月4日)
実態の把握ができていなければ、目標を設定してもうまくいかない可能性があります。組織開発によって、臨機応変に変化し続けられる組織、強い組織をつくっていくためには、まず現状の組織の問題がどのようなプロセス(人と人の関係性、部署間のコミュニケーションなど)から引き起こされているかを「見える化」する必要があります。
実際、社員が消極的、モチベーションが低いなどの問題にはいろいろな原因が絡んでいるものです。安易に施策を決める前に、まずは無記名の従業員意識調査などを実施し、現実を徹底的に把握するのが効果的です。また、施策を実施してからの検証やフィードバックも大切です。
組織改善活動のキーマンである組織長も、実践した施策の効果がタイムリーに検証できないとモチベーションが低下したり、施策の見直しを適切に行えなかったりします。そのため、組織改善活動が中途半端な状態になるケースもあります。継続した調査・検証を行い現場へフィードバックすることが必要です。
組織開発の成功に有効な「パルスサーベイ」とは?
組織改善活動については、目的にもよりますが四半期に1回、1カ月に1回、あるいは週1回などあまり期間をあけずにタイムリーに効果を検証していくことが大切です。このような調査手法は「パルスサーベイ(Pulse survey)」と呼ばれ、近年日本でも導入する企業が増えています。
パルスサーベイにより結果をリアルタイムに把握し対策に活かしていくことは、組織開発の成功を後押しします。また、企業と人、管理職と社員のコミュニケーション促進にもつながります。なによりパルスサーベイはビジネス環境がスピーディに変化するいまの時代に適した調査手法だといえるでしょう。