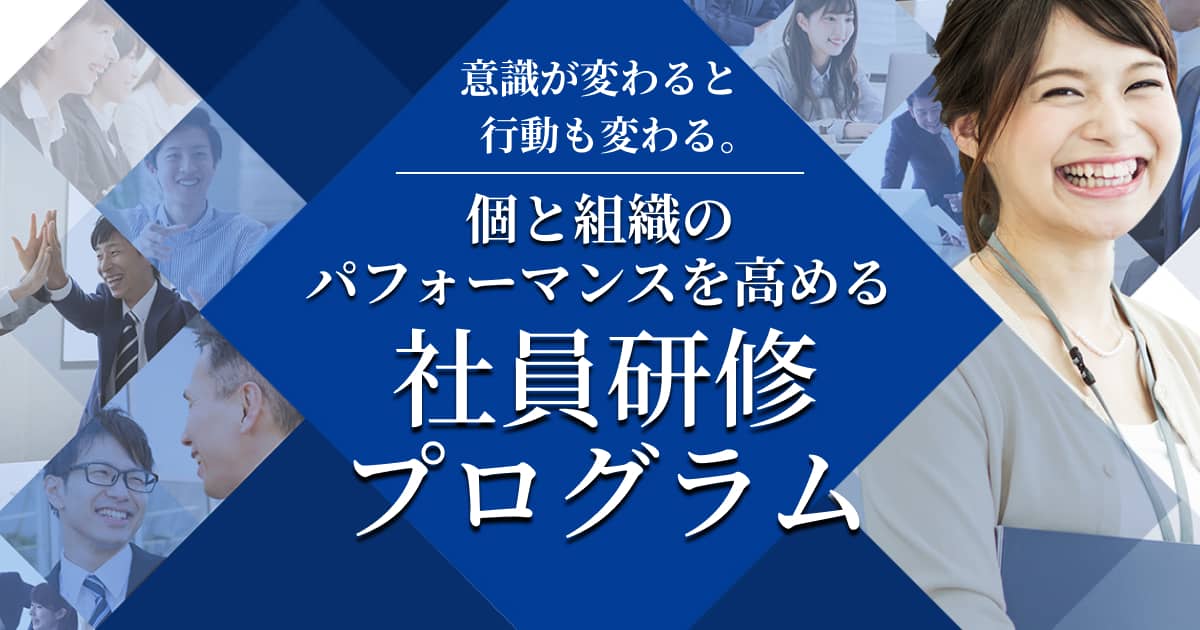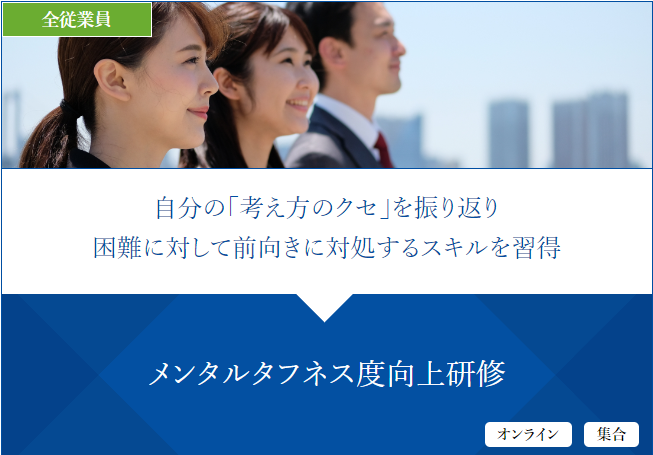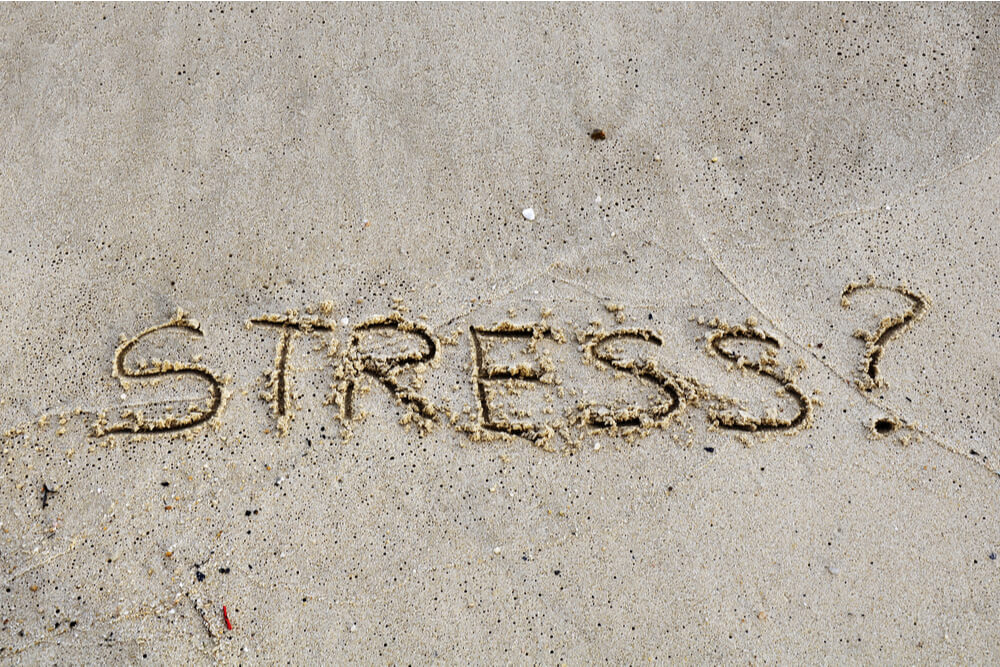職場のメンタルヘルス対策においては、従業員が自分自身でストレスに対処する「セルフケア」の取り組みが不可欠です。自らのストレスに早めに気付き、適切なセルフケアを通して心身の健康維持を図ることは、従業員個人にとってプラスになるだけではなく、組織の運営、安定的な成長という意味でもメリットがあります。今回は、セルフケアの重要性の他、職場や自宅でできるセルフケアについてご紹介します。

目次
メンタルヘルスにおけるセルフケアとは

はじめに、職場のメンタルヘルス対策の考え方について整理しておきましょう。
職場のメンタルヘルスケア「4つのケア」とは
厚生労働省は、「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」において、企業のメンタルヘルス対策として「4つのケア」の推進を掲げています。4つのケアの特徴と役割は以下の通りです。
・セルフケア
従業員が自分自身で行うケア。自らのストレスに気付き、適切な対処によってメンタル不調の未然予防につとめます。
・ラインによるケア
部下を持つ管理監督者が行うケア。管理監督者は日ごろから職場に目を配り、職場環境の改善や部下の異変(※)の早期把握と対応を行います。併せて、メンタルヘルス不調者の職場復帰支援などを担当し、職場の活性化を目指します。
※部下の異変の例:早退、遅刻、無断欠勤、ミスの増加、不自然な言動、服装や身だしなみの乱れ など
・事業場内産業保健スタッフ等によるケア
産業医、保健師や看護師、心理職など、専門的な知識を持つ産業保健スタッフと人事労務管理スタッフが連携して行うケアです。効果的なセルフケア、ラインケアにつなげるため、従業員や管理監督者を支援したり、メンタルヘルス対策の企画・立案や推進などを行ったりします。
・事業場外資源によるケア
会社以外の専門的な機関や専門家のサポートを受けて実施するケア。事業場内の産業保健スタッフと外部の専門機関が協力し、より効果的な施策推進を目指します。
<事業場外資源によるケアの例>
- 従業員支援プログラム(EAP)
- 労災病院・診療所
- 都道府県産業保健推進センター
- 地域産業保健センター など
セルフケアとは
セルフケアは、4つのケアの中で最も基本的な対策で、メンタル不調の予防が目的です。メンタル不調のサインは、ほとんどの場合単純な身体の疲れや精神面の変化として現れますが、本人でも気付かないことがあります。従業員が心の健康に関する正しい知識を身につけ、自分自身のメンタル不調の兆候にいち早く気付き、自発的にケアをすることで、悪化を未然に防ぐことができるでしょう。企業は、従業員に対してメンタルヘルスに関する教育や研修を実施する他、自らの抱えるストレスに気付けるきっかけを提供することが求められます。
メンタルヘルスにおけるセルフケアの重要性

企業がメンタルヘルス対策を効果的に進めていくうえでは、メンタルヘルスに関する深刻な問題が起きてから対処するのではなく、「セルフケアによる未然防止」が特に重要です。従業員個人のセルフケアを支援することは、生産性向上や離職率低下といった健全な企業運営の実現という観点でもプラスの影響を与えます。
従業員の心の健康維持・促進
すべての従業員がメンタルヘルスに関する基本的な知識を持ち、正しいセルフケアの方法を知っていると、自分自身や他の従業員のメンタル不調に気付きやすくなります。メンタル不調を自覚したうえで、いち早く適切な対処ができると、従業員の心身の健康維持につながり、ウェルビーイングの実現にも寄与するでしょう。
生産性の向上
仕事のパフォーマンスは、ポジティブで意欲的な心理状態の時に上がるといわれています。適切なセルフケアによってメンタル不調を未然に防ぎ、心身が安定した状態で働けていると、その従業員が本来持つ判断力や思考力、クリエイティビティが発揮されます。結果として生産性が上がり、業績の向上にもつながるでしょう。
休職率・離職率の低下
メンタルヘルス不調からうつ病などの疾患を発症すると、休職や離職せざるを得ないケースもあります。セルフケアによってメンタル不調の悪化を防げれば、離職率の低下も期待できます。
メンタルヘルスにおけるセルフケアを始める時期って?
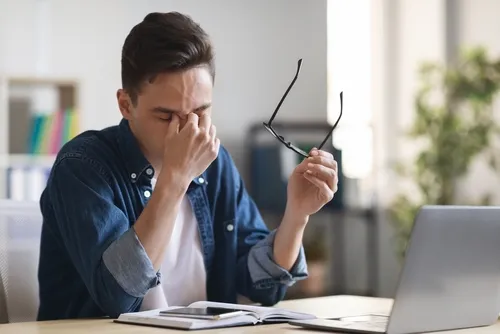
私たちは、常にさまざまなストレスを感じながら生活しています。ストレスに強い方だと思っていても、無自覚にストレスを溜め込んでいる可能性もあるでしょう。例えば、眠れない、イライラする、なんとなくだるさを感じるなど、ちょっとした身体の不調はストレスのサインかもしれません。「一時的なものだ」「すぐに治るだろう」とこれらを軽視して放置してしまうと、さらにメンタル不調が悪化するおそれもあります。今、自分はどの程度ストレスを感じているのか、最近ストレスを感じるような出来事を体験したかなど、自分の心身の状態を観察し、ストレスサインに気付いた時には、なるべく早くセルフケアを始めることが大切です。
メンタルヘルス不調のサイン
メンタル不調のサインは、感情や思考、体調、日々の生活習慣など、あらゆるシーンに表れます。ここでは、メンタル不調を疑うべき兆候を具体的にご紹介します。

感情・思考面のサイン
メンタル不調のサインとして、感情や考え方に表れる変化は以下の通りです。
<感情・思考面に表れるサイン>
- 気分が沈みやすくなる、憂鬱な気持ちが続く
- 不安に駆られて落ち着かない
- わけもなく涙が出る
- 何をするにもおっくうで気力がない
- 集中力が続かない
- 以前より怒りっぽくなった
- 何をしても楽しいと感じられない
- 消えてしまいたいような気持ちになる
- 自分の悪口を言われているように感じる
- どうせ失敗すると悪いほうにばかり考える
- 自分を責めがちになる
体調面のサイン
体調の変化も、メンタル不調のサインである可能性があります。
<体調面で気を付けたいサイン>
- なかなか寝付けない、ぐっすり眠れない、寝すぎてしまう
- 食欲がわかない、食事をおいしく感じない、食べすぎてしまう
- 肩こりや頭痛が続く、疲れがとれない
- 汗が止まらなくなる
- 胸がどきどきして息苦しく感じることがある
- 体がだるく、やる気が起きない
- お腹の調子が悪く、便秘や下痢が続く
生活面のサイン
生活習慣や行動面の変化は、本人ではなく周囲の人が気付くことも多いでしょう。
<生活面で気を付けたいサイン>
- 遅刻、早退、欠勤が増える
- 生活リズムが乱れる
- 単純なミスが増える
- お酒やタバコ、カフェイン飲料などの摂取が増える
- 身だしなみに気を使えなくなる
- 浪費しやすくなる
職場や日常でできるセルフケアの方法

セルフケアには、さまざまな方法があります。ただし、セルフケアを義務と捉えると、それ自体がストレスになりかねないため、自分に合った方法を選ぶことが大切です。ここでは、職場などでも気軽に実践できるアイディアをご紹介します。
深呼吸や軽いストレッチをする
深呼吸や軽いストレッチは、副交感神経の働きを優位にするため、心拍数を下げて体の緊張を緩和させ、リラックス状態にしてくれることがわかっています。椅子に座ったまま手足を伸ばしたり身体をひねったりすると、筋肉の凝りが多少とれるだけではなく、気持ちの面でもすっきりするでしょう。
社内で実践できるセルフケアの方法は、以下の記事でもご紹介しています。
気分転換をする
気分転換をしたり、一息つける時間をつくったりすることも大切です。軽くストレッチをする、遠くの空を眺める、最近楽しかったことを思い出すなど、気分転換になることを試してみると良いでしょう。
また、好きな飲み物を飲む、気心の知れた同僚と過ごし、笑ってコミュニケーションをとることも、リフレッシュにつながります。作り笑いでも、笑うことはストレスを軽減する効果があるといわれているため、特に意識すると良いかもしれません。
自宅や休日にできるセルフケアの方法

続いては、帰宅後や休みの日など、まとまった時間の取れる時に取り組めるセルフケアをご紹介します。リラックスできることや楽しいことなど、自分に合ったセルフケアの方法を複数集めた「コーピングリスト」を作り、その時々で適した方法を選び取って行うのもおすすめです。
コーピングリストの作り方については、以下の記事で詳しく紹介しています。
十分な休息・睡眠を取る
生活習慣を整えることを意識し、十分な休息と睡眠をとりましょう。睡眠は脳と身体の休息、回復という役割を担っています。十分に時間が取れていなかったり、睡眠の質が悪かったりすると、疲労感や情緒不安定な状態に陥り、さらにストレスが増すこともあります。寝付きが悪いからとスマホを操作する、アルコールやカフェインが入った飲み物を飲むなどすると、睡眠の質を低下させるため注意が必要です。
基本的なことではありますが、バランスの良い食事や定期的な運動、入浴(湯船に浸かる)などの規則正しい生活を心がけることも重要です。
趣味や身体を動かす活動をする
気分をリフレッシュするため、趣味や好きな活動をすることも一つの方法です。例えば、スポーツやジョギング、ストレッチやヨガなどの体を動かす活動のほか、映画鑑賞や音楽鑑賞、ゲームなどの趣味を楽しむ、マッサージやアロマテラピーなどのリラクゼーションも効果的です。一つでも良いので、普段からできるセルフケアの方法を持っておきましょう。
周囲の人に相談する
ストレスを一人で抱え込まず、同僚や先輩、プライベートの友人や家族、専門家など周囲の人に話を聞いてもらうことも大切です。誰かに相談することは、ストレスによる心身へのネガティブな影響を弱めるといわれています。心の中のモヤモヤや不安を話すだけでも、心理的な安心感を得られるでしょう。
セルフケアを効果的に行うポイント

従業員のセルフケアをより効果的なものにするためには、企業側からの積極的な支援が不可欠です。最後に、セルフケアのサポートとして有効な取り組みをご紹介します。
ストレスに関する基礎知識や対処法のインプット
今どのくらいストレスを抱えているのか、どの程度疲れているのかなど、自分の心身の不調に気付けるようになるためには、継続的に自らと向き合うことが大切です。そのためには、従業員がストレスやメンタルヘルスに関する正しい知識を身に付けられる研修の実施が有効です。ストレスの原因や心身のストレス反応を正しく把握したうえで、適切なセルフケアにつなげます。
役職によってストレスの要因が異なることもあるため、管理職、若手社員、新入社員などのように、階層ごとに内容を分けて行うこともおすすめです。「組織としてストレスに適切に対処する」というメッセージを明確に発信し、繰り返し学べるよう定期的に実施することが望ましいでしょう。
アドバンテッジリスクマネジメントでは、ストレスの基礎知識から対処法について学べる研修プログラムを提供しています。
ストレスについての知識をはじめ、ストレスに自ら対処するための具体的な方法を習得します。アウトプット重視・体感型の内容で、受講者の気づきを促します。また、すぐに使えるリラクゼーションなども取り入れた実践的な内容となっています。
■ストレスマネジメント力向上研修
適性検査「アドバンテッジ インサイト」の結果からわかる自分のストレス対処傾向をもとに、ストレスと上手に付き合う方法を学ぶ研修です。採用時の適性検査に「アドバンテッジ インサイト」を用いることで、入社後にその結果を活用した研修を行うことが可能です。アウトプット&ワークを中心に、ストレス対処力(コーピング)、ストレス緩和力を高めていきます。
「思考のクセ」の理解および改善促進
人にはそれぞれ考え方の「クセ」があります。ついネガティブな方向に考えてしまう思考のクセを、「認知の偏り」と言います。
<「思考のクセ」の例>
- こうなったのは自分のせいだ」と思い込む
- 「〇〇すべき」「〇〇であるべきだ」と固定観念で自分を縛る
- 「きっとこう言われるだろう」などと悪い方向に決めつける
- 根拠もないのに悲観的になる
このようなマイナスの認知を減らすには、自身にこうしたクセがあることに気付き、それを修正するとともにプラスの認知を増やしていくことが大切です。従業員自身がこれを理解することで、早い段階でストレスを処理できるようになり、適切なセルフケアにつながります。
自分の「考え方のクセ」を振り返り、困難に対して前向きに対処するスキルを習得。親しみやすい観点で整理された「ストレスを感じやすい考え方のクセ」について触れ、段階的に検討するワークで自分自身の認知も振り返ります。
1on1などを通じてコミュニケーションを活性化
ラインケアにも通ずるものですが、職場におけるコミュニケーションを活性化させることも大切です。悩みやモヤモヤしていることなど、些細な内容であっても雑談/相談しやすい環境であれば、ストレスに直面した際にチームのメンバーや上司に話を聞いてもらうことで、ストレスに上手く対処する方法を見出せるかもしれません。困難な状況をポジティブに捉え直せる可能性もあるでしょう。管理職に1on1などの実施を促すことも有効な方法の一つです。
ストレスチェックを活用する
セルフケアの重要性を従業員に理解してもらうきっかけ作りとして、ストレスチェックを活用しましょう。ストレスチェックの結果は、自分自身のストレス状況がデータで可視化され、自身の現在の状態を知ることができるため、セルフケアを意識するきっかけとなります。また、企業としても、組織全体が抱えるストレスの状況を把握することも可能なため、今組織で生じている課題の発見にもつながります。
ストレスチェックの結果をすぐに従業員へフィードバックし、カウンセリングやeラーニングなど必要な対策を案内するなど、従業員がセルフケアに活かせるような環境づくりも同時に進めましょう。
セルフケアでメンタル不調を未然に防ぐ

働く中でのストレスは、避けて通れないものと言わざるを得ません。ある程度ストレスがかかることを前提として、対策のための知識やセルフケアのテクニックを身に付けておくことが大切です。メンタルヘルス対策は、不調を未然に防ぐことが何よりも重要です。企業も、従業員の心の健康が組織にとってプラスになることを理解し、セルフケアの支援につとめましょう。