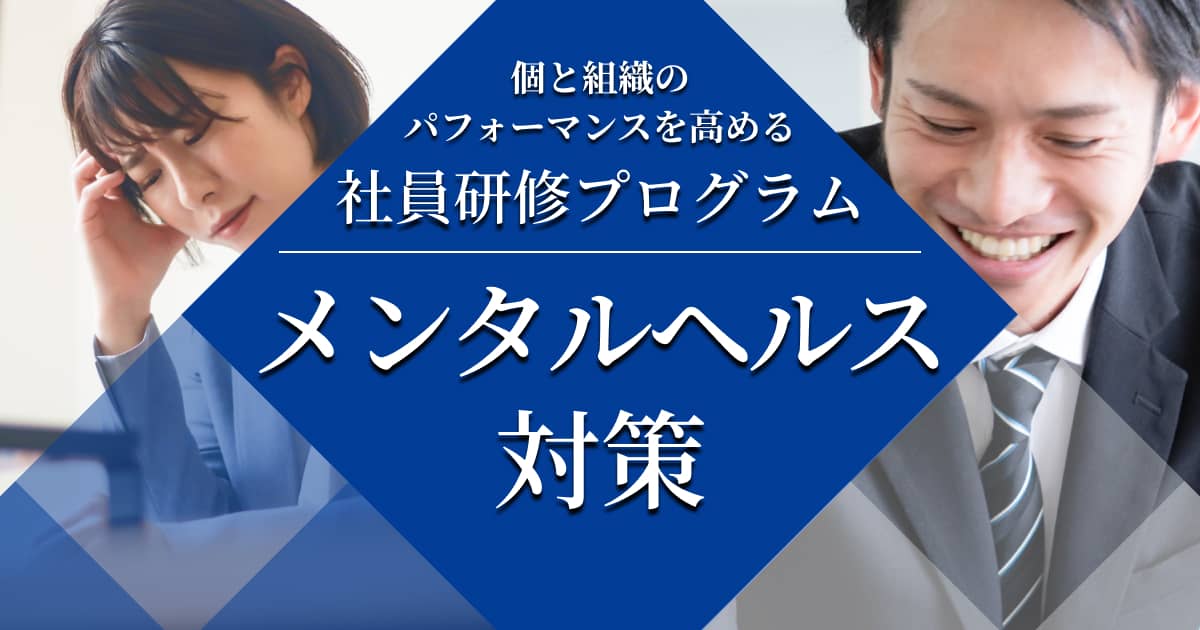レジリエンスとは、「しなやかな強さ」「精神的回復力」などと訳され、挫折や難局から回復する精神的な力を表す言葉です。困難を乗り越えていくために不可欠な力として注目を集めていますが、ビジネスの分野でも、企業が刻々と変化する時代を生き抜いていくための力として重要視されています。今回は、レジリエンスの意味や向上のメリット、組織のレジリエンスを高める方法などについて、詳しく解説します。

目次
レジリエンスとは?

はじめに、レジリエンスの意味やビジネスシーンで注目を集めている理由について解説します。
レジリエンスの意味
レジリエンスとは、困難な状況から気持ちを立て直す「精神的な回復力」のことです。もともとは物理学で用いられていた言葉で、「外から力を加えられて変形した物体が、もとの形に戻ろうとする力、歪みを跳ね返す力」を示していました。
心理学では、「しなやかな強さ」「精神的回復力」「復元力」などと訳され、挫折や苦境から回復する精神力という意味があります。ビジネス現場においては、“想定外の出来事に対し、冷静かつ臨機応変に対応できる力”や、“新しい環境や変化にしなやかに対応できる力”と捉えられています。
ビジネスにおけるレジリエンス
ビジネスにおいては、組織と従業員個人、2つのレジリエンスが重要です。組織のレジリエンスとは、働き方改革による長時間労働の制限やメンタルヘルス施策をはじめ、ハラスメント防止、ダイバーシティ施策など、あらゆる変化に柔軟に対応できる組織力のことです。
一方、個人のレジリエンスとは、仕事上で困難な壁にぶつかった時や、未経験の業務を任された時など、外部環境の変化にしなやかに適応し、乗り越えていく対応力や思考を意味しています。
レジリエンスが注目される背景
ダイバーシティやDXの推進、リモートワークの導入など、従来に比べて労働環境は大きく変わっています。働き方が多様になった分、新しい業務や、今までとは異なる手順などにストレスを感じるケースが増えたこともあり、それらに適応する力として、レジリエンスが注目されるようになりました。また現代のビジネス現場では、年功序列や終身雇用といった概念から、成果主義を重視した働き方にシフトしています。
加えて、現代はVUCA※時代と呼ばれる、変化が激しく予測困難な時代が到来しています。企業を取り巻く環境が刻一刻と変わり、新たなニーズやルールへのすみやかな対応が求められる中では、ビジネスモデルやプロセスが複雑化し、業務負担が増加していることは否めません。その時々の環境に適応し、目標達成に向けてポジティブに努力できる人材を育てるためにも、レジリエンスの重要性が注目されています。
例えば欧米では、リーマンショックをきっかけに、多くの企業が従業員に対してレジリエンス研修を提供しました。これは、心身の安定を保ちながら不況を乗り越え、仕事上の変化を受け入れるという新しい挑戦に対し、柔軟に適応できる人材育成をしようとしたためです。
※VUCA(ブーカ)…Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉
レジリエンスとメンタルヘルス、ストレスコーピングなどとの違い
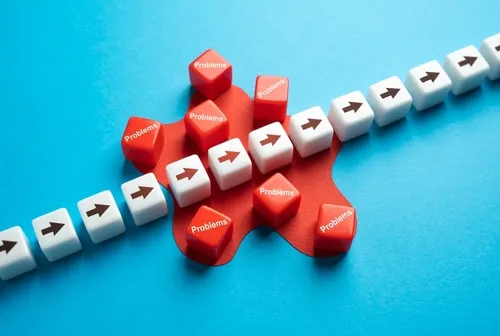
レジリエンスと似た言葉について整理しておきましょう。「メンタルヘルス」「ストレス耐性」「ストレスコーピング」との言葉の違いを解説します。
「メンタルヘルス」との違い
「メンタルヘルス」は、直訳すると「心の健康」「精神的健康」という意味であり、「メンタルヘルス対策」は ストレスや悩みを軽減したり、メンタル不調を予防したりするための一連の取り組みを指します。レジリエンスは、ストレスや困難に対処できる力、上手く乗り越えられる力を意味するため、メンタルヘルス対策とも関連が深いといえます。
「ストレス耐性」との違い
レジリエンスと近い領域で使われるストレス耐性とは、「ストレスへの抵抗力」を表します。どの程度のストレスに耐えられるか、ストレスそのものに気づく力や、ストレス要因をなくす、弱められる力、ストレスをポジティブな方向に捉え直せる力など、複数の要素から構成されるものです。
一方、レジリエンスは「ストレス状態から立ち直る力」を表すため、着眼点が異なります。ストレス耐性が高い人は打たれ強いイメージがあることから、ストレス耐性が高い=レジリエンスが高いと認識されることも多いかもしれませんが、必ずしもそうではありません。
「ストレスコーピング」との違い
「ストレスコーピング」とは、ストレスに対して上手く対処しようと意図的に行うセルフケアのことです。ストレスに対処するための「手段」という意味合いが強いですが、レジリエンスは「その人自身に備わったストレス対処の力」といえます。
レジリエンスの危険因子と保護因子
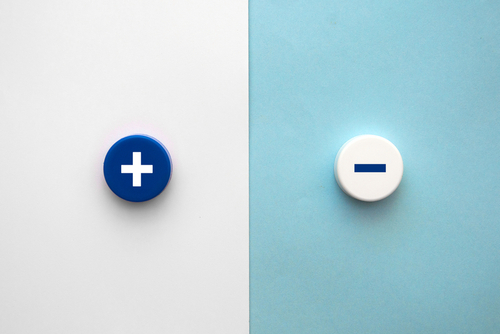
レジリエンスを知る上で理解しておきたい用語として、「危険因子」と「保護因子」があります。レジリエンスは、「危険因子」に対応、克服する場面で発揮されるものです。そして、個人のレジリエンスを高めるためには、質の高い「保護因子」を増やすことが重要だといわれています。
【危険因子】
危険因子とは、強いストレスや困難な状況をもたらす原因のことです。例えば、人間関係や病気、貧困、虐待の他、戦争や災害などが当てはまります。
【保護因子】
保護因子とは、困難やストレスからの立ち直りを促す、すなわちレジリエンスを促す要素のことです。個人の性格や思考の特性といった内面的な要素だけではなく、良き相談相手がいるかなど、外部環境も影響します。
レジリエンスを高めるメリット

続いて、レジリエンスを高めるメリットを、個人・企業それぞれの観点からご紹介します。
【個人】問題解決能力が高まる
個人のレジリエンスが高いというのは、難しい状況であっても、ポジティブかつ柔軟に物事を捉えられ、目標を達成するためにどのような行動をすれば良いのか、広い視野に立って多面的に考えることができる状態といえます。
最適解を探すための努力や挑戦を続けられることから、問題解決能力が高まります。上手く対処できた、解決できたという成功体験が重なれば、「自分ならできる」という自信にもつながるでしょう。万が一失敗したとしても、「ここは上手くできた」というように、失敗を前向きに捉えて認められるため、モチベーションを維持できます。
【個人】ストレス耐性が高まる
従業員のレジリエンスが高い状態とは、困難に陥っても悲観的になりにくく、ストレスへの耐性が身についた状態です。ストレスを感じた時にも、自分の感情を理解し、しなやかに対処すれば、そのストレスと上手に向き合えるでしょう。また、心身の健康を維持しやすくなれば、ストレスが原因で体調を崩すといったメンタル不調の未然予防にもつながり、休職・離職リスクの低下も期待できます。
【企業】変化に強い組織になる
一人ひとりのレジリエンスを高めると、変化に強い組織になるため、環境変化やリスクへの対処がスムーズになります。例えば、企業の方針転換や新規事業を始める時に、難しい課題や厳しい状況に直面したとしても、すばやく現状を把握し、適切な対応を取れるようになるでしょう。
【企業】組織の生産性・エンゲージメントが向上する
レジリエンスの高い従業員は、周囲の環境やストレス要因に左右されることなく、安定的に高いパフォーマンスを発揮できます。一人ひとりの生産性が上がれば、組織全体としても計画や目標を上回る成果を得られるでしょう。前向きに仕事に取り組めているということは、従業員のエンゲージメントが高い状態ともいえ、良好な組織風土の醸成にもつながります。
レジリエンスが高い人と低い人の特徴

レジリエンスが高い人、低い人には、それぞれ以下のような特徴があります。
レジリエンスが高い人の特徴
<レジリエンスが高い人の特徴>
- 発想や考え方が柔軟である
- 自分の感情を的確に把握した上で行動でき、上手く切り替えられる
- 周囲の人達と良い関係を築ける
- 自分の長所を認識している
- 困難なことに直面しても適切に判断し、すぐに諦めない
- 新しいことや知らないことに興味を持ち、積極的にチャレンジする
レジリエンスが低い人の特徴
<レジリエンスが低い人の特徴>
- 気持ちの切り替えが得意でない
- 発想や考え方の柔軟性が乏しい
- 自分にも人にも厳しく、一人で抱え込みやすい
- 消極的で新しいチャレンジをしない
- 自分の短所ばかり気にしている
- 困難なことに直面したらすぐ諦める
レジリエンスを高める方法

企業のレジリエンスを向上させるには、従業員一人ひとりのレジリエンスを高めることが必要です。レジリエンスは、後天的に高めることができる力とされています。ここからは、個人と企業のレジリエンス力を向上させる具体的な方法をご紹介します。
【個人】自分自身の思考の傾向を把握する
自分を高い次元から客観的に見て、冷静に自己分析をする(メタ認知)ことによって、自分自身の思考の傾向を把握しましょう。
人には、それぞれが陥りがちな否定的あるいは偏った思考のパターンがあります。例えば、「何をやっても上手くいかないから、この先もきっと失敗が続くだろう」と思い込んでしまう、「あの人に嫌われているから、コミュニケーションがスムーズにできないんだ」と飛躍した考え方をする、「結果が出なかったから、今までの努力も全て無駄だったんだ」と、0か100かで物事を捉えがち、などが挙げられます。
自分の長所や短所、価値観、過去の成功/失敗体験などから、思考の傾向を分析・把握することで、否定的な思考パターンから抜け出すヒントを得られるでしょう。このように自分の感情を適切に察知し、上手く扱う能力を指す「EQ」については、以下の記事でも詳しく解説しています。
【個人】自尊感情や自己効力感を高める
自尊感情とは、自分自身には価値があると感じ、自分を好きでいられる、大切に思える感覚や状態のことです。自尊感情を高めるためには、まず他人と自分を過剰に比較することをやめましょう。自分の良いところに目を向け、肯定し、「私は価値のある人間だ」「何があっても自分を尊敬する」という気持ちを持つことが、ありのままの自分を受け入れることにつながります。
自己効力感とは、自分の可能性を信じることです。「自分ならできる」という自信を持っているため、自分の感情に対して適切に行動でき、困難があった時も落ち込みすぎません。自己効力感を上げるには、成功体験を増やすことが重要です。
一人でやり遂げるだけではなく、誰かのサポートや助言を受けて困難な状況を乗り越える、といったような経験でも良いでしょう。主体的な行動を成功につなげることが大切です。成功体験により、良い評価を受けたり、できることが増えたりすれば、自分の自信にもつながります。
【企業】心理的安全性の高い職場づくりを行う
レジリエンスを高めるためには、心理的安全性の高い職場づくりも重要です。心理的安全性とは、チームや部署のメンバー一人ひとりが、自分の考えを気兼ねなく発言でき、安心して自然体の自分でいられる状態のことです。ミスや失敗を責められる、ネガティブな反応に怯えて自由に発言ができないような環境では、レジリエンスの向上は目指せません。
困った時にチームのメンバーにサポートを求めることができる、コミュニケーションが円滑で、業務に関する相談や議論が活発に行えるなど、従業員が主体的に行動できる環境づくりを行いましょう。
【企業】ビジョンやミッションの浸透を図る
自社のビジョンやミッションを明確にし、従業員へ浸透させる取り組みも有効です。ビジョンとミッションの共有・理解によって、企業と従業員の目指す方向を一致させることができていれば、従業員はそれらの実現のために自信を持って行動できます。全員が一丸となってビジネスを前進させることができる上、難しい状況に直面したとしても、ビジョン・ミッションに基づいて迷わず判断できるようになります。
浸透のためには、ビジョンやミッションを一度掲げて終わりではなく、従業員に向けて繰り返し提示すること、そして個々の仕事が組織のビジョン・ミッションにどう紐づいているのかを理解してもらう機会を設けることが大切です。
【企業】専門的な知識が得られる研修を実施する
レジリエンスを高めるには、研修やセミナーを受けるのもおすすめです。専門的な研修を受けることで、レジリエンスだけではなく、メンタルヘルスやストレスに関する正しい理解が深まります。これにより、プレッシャーに負けず、最善のパフォーマンスや結果を出すための力を身につけることができます。
当社アドバンテッジリスクマネジメントでは以下のような研修サービスを展開しています。
レジリエンスに向いた思考法と向かない思考法

レジリエンスを高めるためには、自分の思考を意識的に変えていく必要があります。レジリエンス向上を目指す上でチェックしておきたい思考法と、NGな思考の例をご紹介します。
ABC理論
ABC理論とは、アメリカの臨床心理学者・アルバート・エリスが提唱した思考法で、Activating events(出来事)、Belief(信念、認知)、Consequences(結果)の頭文字を取ったものです。同氏は、「出来事(A)そのものが、心理的な結果(C)につながる」のではなく、「出来事(A)を、どう捉えるか(B)によって結果となる感情・行動(C)は変わる」と説きました。Beliefは物事の「受け止め方」や「解釈」、あるいは「思い込み」と訳されることもあります。
【ABC理論の例】
A:同期が先に昇進した
B(ネガティブ):私も頑張っているのに、なぜ評価されないのだろう?
C(ネガティブ):イライラ・落胆して仕事のモチベーションが低下する
A:同期が先に昇進した
B’(ポジティブ):同期が頑張っていると励みになる。彼のように、私も頑張ろう
C’(ポジティブ):仲間の昇進が刺激になり、より意欲的に仕事に取り組む
ABCDE理論
ABCDE理論とは、ABC理論を拡張した思考のフレームワークで、出来事、認知、結果のABCに、Disputation(論証)、Effect(影響)のプロセスを加えたものです。ネガティブな捉え方をポジティブな思考・感情に転換していくための手法です。
論証(D)では、ネガティブな思考・捉え方(B)に反する論拠を見つけます。これにより、新しい思考のパターンが生まれ(E)、ポジティブな結果(C)に変わります。論証(D)で柔軟な考え方ができると、ネガティブな思考にとらわれにくくなるのです。
【ABCDE理論の例】
A:同期が先に昇進した
B(ネガティブ):私も頑張っているのに、なぜ評価されないのだろう?
D(Bに反する論拠):彼が昇進したからといって自分が優れていないというわけではない
E(新しい思考パターン):不足している部分もあるかもしれない、もっと頑張ろう
C(ポジティブ):より意欲的に仕事に取り組む
思考の癖やバイアスに注意
先にご紹介したABC/ABCDE理論のように、出来事(A)と結果(C)の間に認知(B)のプロセスがあると、捉え方を変えることで感情を正しく理解し、行動をコントロールできます。しかし、出来事が結果に直結しているという理解では、意識的に変えられる要素がないため、受け身的な状況になり、時に自分自身を苦しめることにつながります。
以下にご紹介するような「思考の癖」や「バイアス」は、必ずしも悪とはいえませんが、レジリエンスを高める観点では望ましいものではありません。また、他人に対してこのような思考を適用すると、期待が満たされず不満やイライラが募ってしまうこともあります。
【例】
全か無か思考:小さなミスをしただけで、「もう失敗だ」「今までの努力が無駄になった」と捉えてしまう
拡大解釈と過小評価:仕事が上手くいっても「誰でもできる仕事だから、大したことはない」「たまたま成功しただけで、次は上手くいかないかもしれない」と考える
フィルタリング:概ね高評価を得られていても、わずかに改善点を言われただけで「評価は低かった」と感じる
すべき思考:「上司は部下より有能であるべきだ」「常に求められる以上の成果を出すべきだ」と考える
レジリエンス向上に必要な6つの要素(コンピテンシー)

個人のレジリエンスの向上に必要な要素として、自己認識、セルフコントロール、精神的柔軟性、楽観性、自己効力感、人とのつながりの6要素が挙げられます。これらの要素は「レジリエンス・コンピテンシー」と呼ばれており、アメリカ・ペンシルバニア大学のカレン・ライビッチ博士が提唱したものです。ここでは、その6つの要素について詳しく解説していきます。
①自己認識
自己認識とは、自分の行動や思考、感情表現、譲れない価値観など「何が自分にとって大切なのか」を認識する能力です。自分の軸は、自分が置かれている状況や目の前の物事を客観的かつ現実的に判断する指標となり、困難な状況から回復するための第一歩となります。ただし、自分の軸に頼りすぎると独断になりすぎるため、他人の意見を取り入れる柔軟さも必要です。
②セルフコントロール
セルフコントロール(自律心)とは、冷静に自分の感情を捉え、行動をコントロールする能力です。人は変化や困難に直面すると、相手と衝突したり、対立したりしてしまうことがあります。そんな時にもネガティブな思考のまま衝動的に行動するのではなく、感情を自分でマネジメントすることで、落ち着いて適切な行動が取れるようになるのです。最近では、自分自身の感情マネジメントに効果的な「マインドフルネス瞑想」などの方法を取り入れる職場も増えています
③精神的柔軟性
精神的柔軟性とは、物事を多角的にかつ本質的に捉える能力です。焦りや不安は視野を狭くしてしまいますが、しなやかな思考があれば、自分の考え方の癖や価値観を自覚しながら他人の意見を柔軟に取り入れられます。多様な考え方を受け止められるので、自分自身の考え方を変化させたり、創造的なアイディアを生み出したりすることも可能です。
④楽観性
楽観性とは、問題解決や目標達成に向けて「自分は今何ができるか」「何を優先すべきか」を的確に判断し、前進できる能力のことです。「この先はもっと良い状況になる」「これは成長のチャンスだ」と、困難や壁を前向きに捉えることが、恐れる気持ちを打ち消します。
⑤自己効力感
自己効力感とは、「自分はできる」と自信を持つことです。どんな状況にあっても自分の可能性を信じることができると、逆境にひるむことなく、勇気を持って進むことができます。困難に打ち勝つことができれば、その自信は補強され、さらなる一歩を踏み出す原動力となるでしょう。
⑥人とのつながり
人とのつながりとは、周囲の人と関わり合い、助け合える信頼関係を築く能力です。ストレスのかかる環境や難しい状況に直面した時、心の支えになってくれる人や相談できる人がいると、新たな解決策や問題点に気づけたり、精神的に安心したりして、困難を乗り越えやすくなります。
変化を柔軟に受け入れる”しなやかな強さ”を育てる
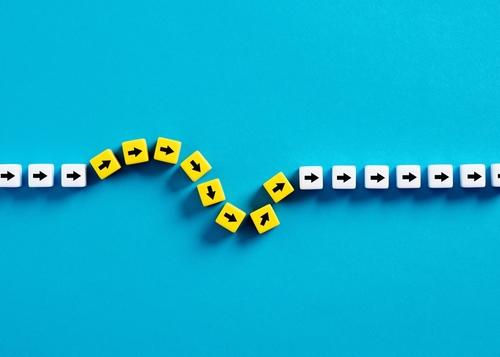
移り変わりの激しい時代の中で、環境の変化に左右されることなく高いパフォーマンスを発揮するためには、変化に適応して困難な状況を乗り越える力「レジリエンス」を高めることが重要です。レジリエンスは、考え方や行動などを意識することで後天的に高められます。企業の主体的な働きかけによって従業員一人ひとりのレジリエンスを高め、ビジネス環境の変化に柔軟に適応できるしなやかな組織づくりを目指しましょう。