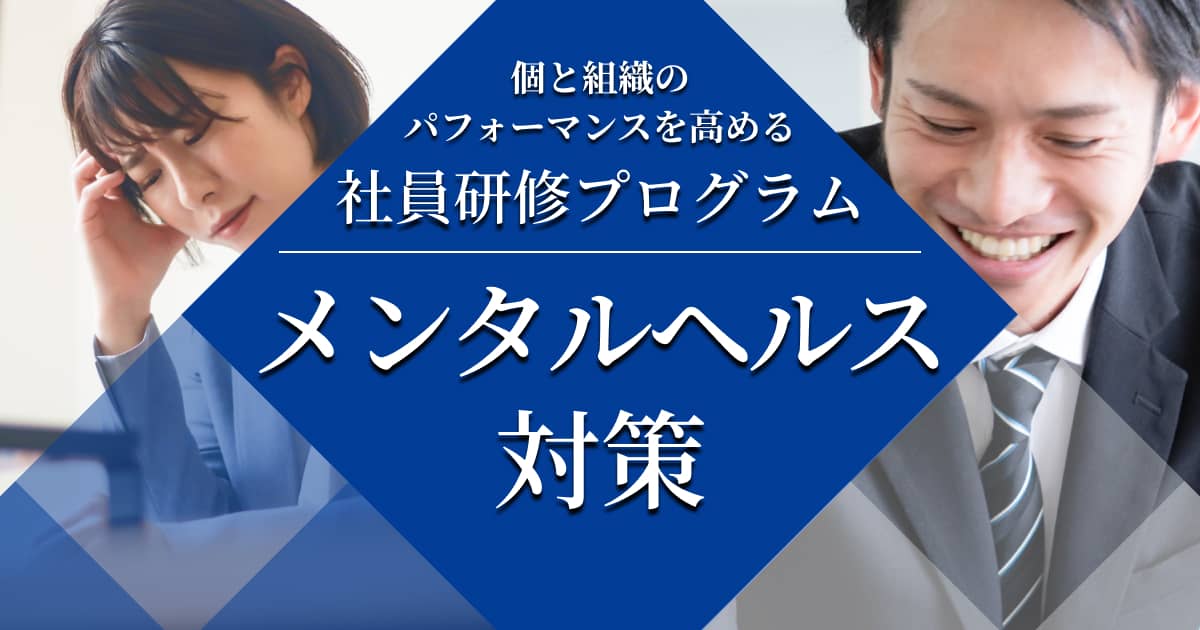現代社会では適応障害など心の病で休職する人が多くなってきており、企業側もメンタルヘルスに関する正しい知識を持っておくことが大切です。そこで今回は、適応障害の症状やサイン、休職になる基準、申請の際に必要な手続きなどについて解説します。併せて、従業員が適応障害をはじめとするメンタルヘルス不調に陥らないよう、企業側がサポートすべきことについても紹介します。

目次
適応障害とは?

まずは、「適応障害」という病気について理解を深めていきましょう。
適応障害とは
適応障害とは、ある特定の状況や出来事に接した時に、「耐え難いほどつらい」と強いストレスを感じ、日常生活を送ることが難しくなってしまうストレス性障害の一つです。ストレスとなる要因は、仕事や人間関係、恋愛、家庭、慢性疾患など個人に関する出来事のほか、地震や水害などの自然災害などさまざまです。 適応障害の症状はうつ病とよく似ていますが、うつ病とは異なり、ストレスの原因から一定の距離を置くと改善するケースがほとんどといわれています。しかし、ストレスから逃れることができないと悪化する恐れがあります。
適応障害の症状
適応障害の症状は大きく「精神面」「身体面」「行動面」に分けられます。それぞれの側面における主な症状には以下のようなものがあります。身体面の症状は、適応障害の初期段階から出現しやすく、内科などの受診を繰り返しているケースも少なくありません。
| 精神面 | ・集中力や体力、意欲の低下 ・感情の起伏が激しくなる ・気分が落ち込む ・焦りや緊張感がでてくる など |
| 身体面 | ・倦怠感や疲労感 ・不眠 ・食欲不振 ・めまいや動悸、吐き気がする ・耳が聞こえにくい、耳鳴りがする ・頭痛・腹痛 など |
| 行動面 | ・飲酒や暴食、たばこが増える ・考えにまとまりがなくなる ・ぼーっとしてしまう ・もの忘れがひどくなる など |
適応障害を疑うサイン
職場において従業員に以下のような兆候や行動が見られたら、それは適応障害のサインである可能性があります。
<適応障害のサイン>
- 遅刻が増えた
- 身だしなみが整わなくなった
- 会話が少なくなった
- 集中力がなく、ミスや間違いが増えた など
適応障害は、一見すると「甘え」や「仮病」などと周囲から見られてしまう場合もあります。上記のサインが見られたり、従業員の様子に少しでも違和感を覚えたりするようなら、産業医への相談を勧めるなど、従業員に寄り添いながら適切に対応しましょう。
適応障害による休職の流れ&手続き

次に、従業員から適応障害を理由に休職したいとの申し出があった際に、企業側が取るべきアクションや手続きの流れを紹介します。休職する従業員が、自分で必要な手続きを調べたり、実行したりするのは大変です。そのため、従業員が安心してスムーズに休職できるよう、企業側のサポート体制を整えておきましょう。
休職に関する規定の確認・書類提出の依頼
休職制度は、法律による定めがないため、運用方法は企業に委ねられています。従業員から休職を希望する申し出があった場合には、まず就業規則で休職の規定を確認し、それに従って手続きを進めます。病気や怪我を理由とする休職の場合、多くの企業では、「休職願(休職届)」と医師の診断書の提出が必須です。原則として、診断書の発行費用は従業員が負担します。
診断書の受理・休職希望者との面談実施
診断書をはじめ、休職に必要な書類が提出されたら、従業員と面談を行い、休業期間や今後のことについて話し合います。産業医を選任している企業の場合は、産業医に相談しながら進めると良いでしょう。
従業員が、主治医から適応障害により休職が必要な状態であると診断されたら、就業規則に照らして休職の可否を判断し、診断書に記載の内容をもとに休職期間を決定します。
また、面談では以下のような休職中の対応についても確認しておきましょう。
<休職前の確認事項>
- ・休職中の連絡方法
- 社会保険料の徴収について
- 療養の経過報告について
- 職場復帰の際の取り決め など
一連の手続きを終えたら、休職辞令を発令し、休職開始となります。
【手続き】休業補償が適用される場合
業務上の理由により労働者が休業する際は、以下の3つの条件を満たす場合に労働災害(労災)と認定され、労働基準監督署から休業補償給付が行われます。
<労災と認められる条件>
1. 労災認定の対象となりうる精神疾患であること
2. 発病前の約6ヵ月間に業務による強い心理的負荷が認められること
3. 個人的な問題で発病したと認められないこと
3つの条件を満たしている場合、以下の流れに沿って申請することで休業補償を受けられます。
<休業補償申請の流れ>
1. 企業が休業補償給付支給請求書と平均賃金算定内訳の事業主欄を記入する
また、医師証明欄を記入する必要もあるため、従業員から証明書を提出してもらう
2. 休業補償給付支給請求書を労働基準監督署に提出
3. 労働基準監督署が該当従業員に支給・不支給の決定をする(通知書が届く)
4. 労災認定を受けた労働者の口座に休業補償が直接振込まれる
最終的に労災であるか否かを判定するのは、労働基準監督署です。そのため医師による証明書があっても、必ず労災認定になるとは限りません。
【手続き】傷病手当金が適用される場合
労災以外の傷病による休職の場合、原則として賃金は支給されません。ただし、健康保険に加入している人が病気や怪我などで働けなくなった場合、傷病手当金が支給されます。支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月です。 精神疾患による労災認定率は30%程度と言われており、認定されるとしても7ヵ月〜1年程度かかります。そのため、労災申請中に健康保険による傷病手当金を受け取っておくことも提案すると良いでしょう。ただし、休業補償と傷病手当金の併給はできません。労災が認められて休業補償が給付されれば、傷病手当金は健康保険に返還する必要があります。
<傷病手当金を受けるための手続き>
1. 休職する従業員が自ら傷病手当金申請書を入手する
2. 従業員が主治医に意見欄の記入を依頼する
3. 本人記入欄を従業員が記入する
4. 企業担当者が「事業主が証明する欄」を記入する
5. 賃金台帳や出勤簿(またはタイムカード)などの必要添付書類を添えて、保険組合や共済組合などに郵送する
6. 審査後、保険組合や共済組合などから労働者に傷病手当金が支給される
適応障害による休職期間満了までの会社の対応

続いては、休職開始から期間満了までの企業の対応について解説します。休職していた従業員が復帰する際は、本人にとって不安が大きいことは想像できます。企業側が行うべきフォローや、復帰できない場合の対応についてチェックしておきましょう。
休職中の従業員と適宜連絡を取る
休職期間中は療養に専念してもらうことが原則ですが、仕事から完全に離れてしまうと孤独感や疎外感を感じてしまうこともあります。事前の取り決めを目安に適宜連絡を取ることと併せて、月に1回程度、近況報告書を提出してもらい、病状の経過などを確認しましょう。
復職の見込みがある場合
休職期間の満了日が近づいてきたら、従業員に復職の意思や、復職できそうか健康状態についても確認します。復職の意思があり、できそうであれば主治医や産業医の意見も聞きながら、職場復帰支援プランを作成しましょう。人事担当者、従業員本人、主治医の三者が内容を把握し、合意を取ることが大切です。
復帰後の早い段階では、頻繁に1対1で面談を実施します。復職した本人は、自分でも気づかないうちに無理をしていることもあります。従業員の健康状態を把握し、業務内容や職場環境が適しているかどうかをチェックしましょう。
休職期間満了日に復職できない場合
適応障害による休職期間の延長については法律の定めがありません。そのため、各企業が設けている就労規則に基づいて対応します。企業によっては、休職期間の満了時に復職できない場合、自然退職や普通解雇の扱いになるケースもあります。ただし、労災による休職の場合は自然退職として取り扱うことはできません。休職した従業員が休職期間満了時に復職できない場合、まずは自社の就労規則を確認して従業員に伝えるようにしましょう。
従業員の適応障害を防ぐための対策

従業員の適応障害を防ぐためには、企業側でもメンタルヘルスケアや職場環境改善に取り組むことが重要です。最後に、企業側ができるメンタルヘルス対策について紹介します。メンタルヘルスケアについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
対策1.定期的なストレスチェックやパルスサーベイを行う
法律により、50人以上の従業員が働く事業場では年1回以上ストレスチェックを実施する義務があります。ストレスチェックを受けることにより、従業員本人が自分のストレスの状態に気づき、セルフケアの必要性を考えることができるため、メンタル不調の未然防止が期待できます。また、強いストレスを感じている高ストレス者には適切な対処を促し、状態の悪化を防ぐことも目的の一つです。
年1回のストレスチェックの実施期間以外の状態把握として、パルスサーベイを行うことも有効です。パルスサーベイは月1回など短期的に繰り返し行われるため変化に気がつきやすいメリットがあります。
対策2.職場環境の改善に努める

適応障害の発生は労働環境や人間関係など、本人以外に原因がある場合もあります。そのため、従業員自身の健康管理ももちろん重要ですが、適応障害に追い込まないような職場環境づくりをすることも大切です。ストレスチェックの結果やパルスサーベイで組織全体のストレス状態を把握し、環境改善の取り組みを進めましょう。
特に、上下関係が発生する組織(ライン)において、部長や課長、マネージャーなどの管理職が適切にメンタルヘルスケアの取り組みを実行できるようにすることが重要です。メンタルヘルスケアや不調予防の取り組みについて知識を深める研修を実施することも効果があります。
また、従業員が自発的に相談できる「心理的安全性」の高い組織を作ることも大切です。メンバー間、または部下から上司に対して思ったことや懸念を口に出しやすく、それを受け止め合うことができる組織であれば、深刻なメンタルヘルス不調に陥る前に問題を顕在化できるため、予防効果も期待できるでしょう。
対策3.セルフケアの大切さを伝える
従業員が自身のストレス状態に気づき、適切に対処できるように促す「セルフケア」は、メンタルヘルス対策において欠かせない要素です。企業としても、セルフケアの重要性を伝え、日常的に取り入れられる環境づくりを支援することが求められます。セルフケアは、自分の健康を守るために必要な知識や技法を身につけ、日常生活において積極的に実施できることを指します。 自分が心地良いと感じることや、心身回復ができると感じることを知っておくのは、セルフケアをする上でとても大事です。身近なセルフケア方法を提案し、従業員のストレスコントロールに役立てましょう。
セルフケアの方法については、以下の記事で詳しく紹介しています。
対策4.悩みを相談できる窓口の設置
産業保健スタッフや外部の専門家などに悩みを相談できるよう、窓口を整えておくことも必要です。カウンセリングは、ストレスなどで心身が深刻な状態になる前でも、誰でも気軽に利用できること、メンタル不調に関することだけでなく、キャリアや自己実現についての相談もできることを発信し、積極的な活用を呼びかけましょう。従業員が安心して使えるよう、相談は匿名でもできること、プライバシーは守られることなども周知します。深刻なストレスを抱えているケースに備え、必要に応じて産業医や専門機関と連携できるよう、その後のサポート体制を整えておきましょう。
適応障害の再発防止のポイント

産業医だけでなく、所属部署の上司などとも連携し、復職後の就業制限などフォローアップを行います。復職して間もない従業員に過度な負担がかからないよう、業務量や内容を調整したり、徐々に慣れてきた後も定期的に面談を行ったりしながら、継続的にフォローすることが大切です。
適応障害による休職。万全のフォローで支えよう。

適応障害は、ストレスによって日常生活を送ることが困難になる病気です。ストレスの原因が明確で、冒頭にご紹介したようなサインが見られる従業員は、適応障害をはじめとしたメンタルヘルス不調に陥っている可能性もあります。従業員から休職の申請があった場合には、就業規定に照らして必要な手続きを進め、休業期間中のフォローも適宜行いましょう。
適応障害は、職場環境や人間関係など、外的な要因がきっかけとなるケースが少なくありません。従業員のメンタル不調を未然に防ぐには、ストレスチェックやサーベイによって定期的に状況を把握するほか、職場環境に問題がある場合は改善に取り組むことが大切です。包括的なメンタルヘルス対策を行い、従業員の心の健康を守りましょう。