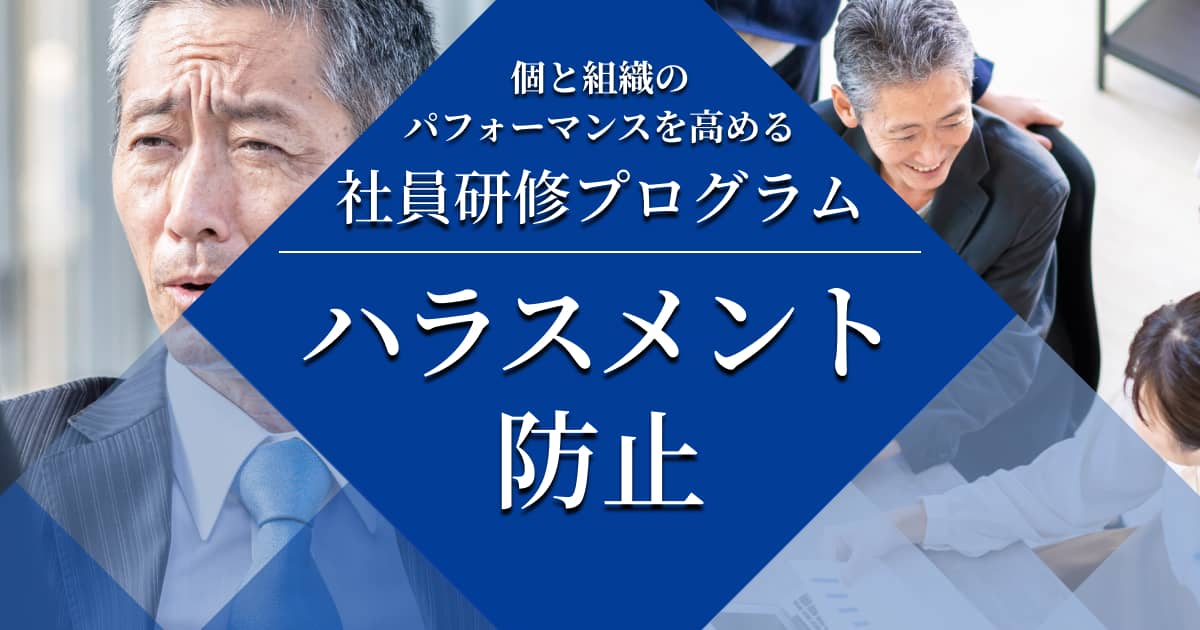職場のハラスメントが社会問題として注目されている今、企業はハラスメント対策を一層強化し、適切な対応や体制の整備をしていかなければなりません。その一方で、「指導とハラスメントの線引きが難しい」「相手のことを思いやった発言がハラスメントだと言われた」など、具体的にどのような発言・行動がハラスメントに当たるのか、判断しづらいと感じることもあるかもしれません。今回は、実際にあった職場のハラスメント事例をご紹介します。ハラスメント問題への理解を深める一助としてください。
目次
ハラスメントとは

はじめに、職場におけるハラスメントの定義と、代表的なハラスメントの種類をチェックしておきましょう。
ハラスメントの意味
ハラスメントとは、ある発言や行動によって、相手に不快な思いをさせたり、脅したり、心身を傷つけたりすることです。相手を傷つけようとする明確な悪意を持たず、無自覚にとった言動であっても、
行為を受けた側が不快に感じた場合、その内容や状況によってはハラスメントに該当することがあります。特に職場のハラスメントは、従業員と企業双方にとって深刻な問題であり、ハラスメントを防止するための取り組みがより一層重要視されています。
代表的なハラスメントの種類
ハラスメントの種類は多岐にわたります。法律や制度上の明確な定義がないものもありますが、職場のハラスメント対策においては、その種類や区別にかかわらず、網羅的に防止のための取り組みを進めていくことが大切です。
<代表的な職場のハラスメント例>
- パワーハラスメント(パワハラ)
- セクシュアルハラスメント(セクハラ)
- マタニティハラスメント(マタハラ)
- パタニティハラスメント(パタハラ)
- モラルハラスメント(モラハラ)
- ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)
- 就活ハラスメント(就ハラ)
- 就活終われハラスメント(オワハラ)
- カスタマーハラスメント(カスハラ)
- ハラスメントハラスメント(ハラハラ)
ハラスメントの種類については以下の記事で詳しく紹介しています。
ハラスメントを放置することのリスク

職場で発生しているハラスメントに対して適切に対応しない企業は、深刻なリスクを抱えます。ハラスメントによって心身ともに傷ついた従業員は、安定的に業務を続けられる状態ではなくなり、業務効率や生産性が低下します。メンタルヘルス疾患を発症した場合、休職や離職につながる可能性があるほか、従業員の命にかかわる事態が起こることも考えられるでしょう。
また、ハラスメントの被害を受けた従業員本人だけでなく、ハラスメント行為を見聞きした従業員が「ここでは安心して働くことができない」と考え、連鎖的に退職が発生する恐れもあります。近年はSNSなどで企業を告発するケースも少なくなく、事実か否かにかかわらず「ハラスメント問題に対応しない企業」と社会に認識されると、企業イメージの低下は避けられません。さらに、ハラスメント被害者から、安全配慮義務違反や使用者責任を追及する訴訟を受ける可能性もあります。
ハラスメント防止は企業の責任

企業は、ハラスメントの防止に向け、適切な措置を実施する法的責任を負います。ハラスメント対策に関連する法律をチェックしておきましょう。
【労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法・ハラスメント規制法)】
事業規模にかかわらず、すべての企業はパワーハラスメントの防止のために雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。罰則はありませんが、対応を怠った場合は指導や勧告を受ける可能性があるほか、悪質なケースでは企業名が公表されることもあります。
【男女雇用機会均等法】
セクシュアルハラスメント(セクハラ)、マタニティハラスメント(マタハラ)の防止を定めた法律です。企業には、従業員のセクハラへの知識や理解を深めるため、「研修の実施その他の必要な配慮」が求められます。
【育児・介護休業法】
マタニティ/パタニティハラスメント(マタハラ・パタハラ)の防止を定めた法律です。育児休業の申請・取得を理由とする不利益な取り扱いの禁止、また制度を利用しようとする従業員への言動によって、当該従業員の就業環境が害されないよう必要な措置や体制の整備を行わなければなりません。
【労働契約法・労働安全衛生法】
企業は、従業員への「安全配慮義務」を負っています。労働契約法第5条に、「企業は従業員の生命、心身の安全を確保したうえで働けるよう必要な配慮をしなければならない」という定めがあり、ハラスメントの実態を認識していながらも、適切に対応しなかった場合はこれに違反します。
また、労働安全衛生法第10条においても、従業員の健康を阻害するような問題の防止、安全と健康の維持、および関連する教育の実施が求められているのです。労働契約法には罰則がないものの、労働安全衛生法は、違反が認められた場合6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられることがあります。
参考:労働施策総合推進法
参考:男女雇用機会均等法
参考:育児介護休業法
参考:労働契約法第5条
参考:労働安全衛生法第10条
実際にあった職場のハラスメント事例

続いては、実際に発生した職場のハラスメント事例をご紹介します。
【パワハラ】複数教諭による後輩教諭への継続的かつ悪質な嫌がらせ
【加害者】30代~40代教員男女4名(A,B,C,D)
【被害者】20代教員4名男女(E,F,G,H)
【発生の経緯】
市立小学校において、先輩にあたる教員4名が若手教員4名に対し継続的に暴言、暴行を行っていた。また、加害者Aは被害者Eの車を故意に破損させる行為を行ったり、加害者Dは飲み会の席で被害者Eに無理やりお酒を飲ませたりした。
【行為による結果】
被害者Eは精神的に不安定な状態になり休職を余儀なくされた。調査委員会は加害者らによる計125の行為をハラスメントとして認定。市教委によって加害者2名は免職、残り2名はそれぞれ停職3ヵ月、減給3ヵ月の処分となった。また、ハラスメントに対し適切な対応を行わなかった前校長ら4名も、停職、減給等の処分を受けた。
【背景・考察】
加害者は「からかい」という認識でこれらの行為に至っており、ハラスメントへの意識の低さがみられました。また、教育現場の職員という閉鎖的な人間環境においては「暗黙のルール」や空気感などの集団規範が一度形成されると変化しづらく、中堅~ベテラン教員の行為について周囲がハラスメントだと指摘することが難しかったことも、ハラスメントがエスカレートした要因の一つといえます。
参考:神戸市教育委員会 教員間ハラスメント事案に係る調査委員会「調査報告書の概要」
参考:神戸市教育委員会 教員間ハラスメント事案に係る再発防止検討委員会 「報告書」
【パワハラ】懇親会への参加強要
【加害者】課長A
【被害者】部下B
【発生の経緯】
課長Aは、職場の仲間とコミュニケーションをとるため毎週飲み会を開いている。部下Bは家庭の事情で欠席が多かったため、Aは「職場の集まりだから参加しなければいけない。なぜ来ないのか?」とたびたび尋ねた。Bは事情を説明したが、Aは「1日くらい平気だろう」と執拗に参加を求めてきた。
【行為による結果】
飲み会に出られないことに対し、繰り返し詰問されることを恐れ、部下Bは仕事に集中できない状態になった。
【背景・考察】
課長Aは、課の結束を高めるためには仕事以外の時間も重要だと感じ、ハラスメントの自覚なく上記のような言動を行っていました。一方で、Bの意思に反して飲み会への参加を強制することは、業務の適正な範囲を超えた過大な要求であり、欠席の理由をしつこく聞き出そうとすることも、パワハラ6類型における個の侵害となり得るため、パワーハラスメントとに該当します。
参考:東京人権啓発企業連絡会「パワハラ事例集」
【パワハラ】業務上の必要性がない配転命令
【加害者】旅館経営者A
【被害者】従業員B
【発生の経緯】
客室係として雇用していた従業員Bは、旅館経営者Aの指示により厨房に配置転換となった。AはBの勤務態度が悪いことを異動の理由として挙げたが、客室係としての業務遂行に著しく悪影響を与えるほどのものではなかった。就業規則には「特段の理由がない限り配置転換には従わなければならない」と示されていたが、客室係の人員に余剰があった/厨房の人員が不足していたという事実も認められなかった。
【行為による結果】
業務内容や勤務形態が大きく変わり、また接客ではない部署への異動となったため、Bは精神的なショックを受けて退職。
【背景・考察】
一般論として、配置転換の命令そのものは違法とはいえませんが、今回のケースにおける異動が業務上差し迫った必要性があるものとは認められませんでした。旅館経営者Aが従業員Bを追放しようと権威を乱用し、嫌がらせという不当な動機によってなされた命令と推認されてもやむを得ないと判断されました。これは、職務上の立場を利用したパワーハラスメントに該当します。
神戸地裁平成14年10月30日判決
参考:厚生労働省「明るい職場応援団」
【セクハラ】不必要な身体接触を求める言動
【加害者】町長A
【被害者】女性職員B
【発生の経緯】
町長Aは、女性職員Bとの雑談の中で「手相を見てあげる」「僕の手すべすべでしょう」などと言って女性の手に触れる、自分の手に触らせることを要求する行為が複数回あった。Bは断りきれず手を差し出し、Aはその手に触れた。他の女性職員に対しても同様の行為を行っていたが、男性職員で同様の行為を求められた人はいなかった。
【行為による結果】
週刊誌報道によって事実が発覚し、加害者である町長Aは辞職した。
【背景・考察】
職場において手相を確認させるような行為は不要であり、町長という地位を背景に、不必要な身体接触を求めるセクシュアルハラスメントに該当します。やむを得ず手を差し出した女性職員Bの行動は、町長Aの機嫌を損なうことを恐れてのものであり、Bの同意があったとは認められません。
参考:岐南町ハラスメント事例に事案に関する第三者調査委員会「調査報告書」
【マタハラ】妊娠に伴う降格
【被告】事業者A
【原告】副主任B
【発生の経緯】
理学療法士である副主任Bが妊娠したため、事業者Aは労基法に基づいて軽微な業務への転換を実施した。転換に際しBは副主任を免じられ、産休・育休から復帰しても副主任の職に戻ることはなかった。男女雇用機会均等法に違反するとして、副主任Bは損害賠償請求訴訟を提起した。
【結果・考察】
事業者Aは、慰謝料と副主任手当全額の支払いが命じられました。簡易な業務への転換は妥当ですが、降格は、職場復帰後も副主任としてのポストを用意していないことを示唆しており、また副主任Bが降格を承諾したとは認めにくく、本人の意向に反するものでした。管理職の地位と手当を喪失したという不利益は重大であり、均等法9条3項の不利益取り扱いに当たり、マタニティハラスメントに該当します。
広島市中央保健生協事件:広島高裁平成27年11月17日判決
参考:厚生労働省「確かめよう労働条件」
【パタハラ】育児休業取得に伴う不利益な取り扱い
【被告】A病院
【原告】男性看護師B
【発生の経緯】
男性看護師Bが育児休業を3ヵ月間取得したが、①就業規則に基づき職能給の昇給を認めず、②育児休業取得を理由に昇格試験の受験資格を認めず、受験の機会を与えなかった。男性看護師Bは、これらを育児介護休業法第10条に違反、また公序良俗にも反しているとして、昇給/昇格した場合の差額分の損害賠償を求めた。
【結果・考察】
第一審では、昇格試験を受けさせなかったことのみ不法行為にあたるとしましたが、控訴審では、育児休業を理由に昇給させなかったことも違法と判断し、損害賠償請求を認めました。男性の育児休業取得に伴うパタニティハラスメントの一例といえます。
医療法人稲門会(いわくら病院)事件:大阪高裁平成26年7月18日判決
参考:公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
参考:独立行政法人労働研究・研修機構日本労働研究雑誌 2015年11月号(No.664)
職場のハラスメントを防ぐポイント

職場のハラスメントを防止するため、企業には多面的な対策が求められます。主な取り組みは以下の通りです。
<企業に求められるハラスメント対策>
【ハラスメント防止に向けた指針・ルールの策定、周知】
ハラスメントを許さないという姿勢を明確に示し、従業員の意識を高めます。
【ハラスメントの発生リスク、実態の把握】
定期的にサーベイを実施し、ハラスメント被害を受けている人がいないか、ハラスメントが発生しそうな兆候がないかを把握します。
【全従業員を対象とした社内教育・研修の実施】
ハラスメントに関する社内教育や研修を行い、ハラスメントについて理解を深めます。適切なコミュニケーションの方法や指導を学び、自らの言動の改善につなげることで、ハラスメントが起きない環境づくりを目指します。
【相談窓口の設置】
さまざまなハラスメント相談に一元的に対応できる、専門の窓口を設置します。相談者のプライバシーは守られること、また相談したことによって不利益な扱いを受けないことなど、安心して相談できる旨を周知しましょう。
詳しくは以下の記事でも解説しています。
意識改革と環境改善で職場のハラスメントを防止

ハラスメント防止は組織として取り組むべき重要な課題であり、決して当事者間だけの問題ではありません。企業として適切な対応を行わなかった場合、法的リスクを追及される可能性があり、社会的評価の低下にもつながりかねません。
ハラスメントを生まない職場環境を目指すには、まず「どのような行為がハラスメントに当たるのか」を理解し、自覚なくハラスメントと認められるような言動をしていないか、自らを振り返ることが大切です。研修や教育の機会を提供し、従業員のハラスメント防止意識を高めることも有効です。