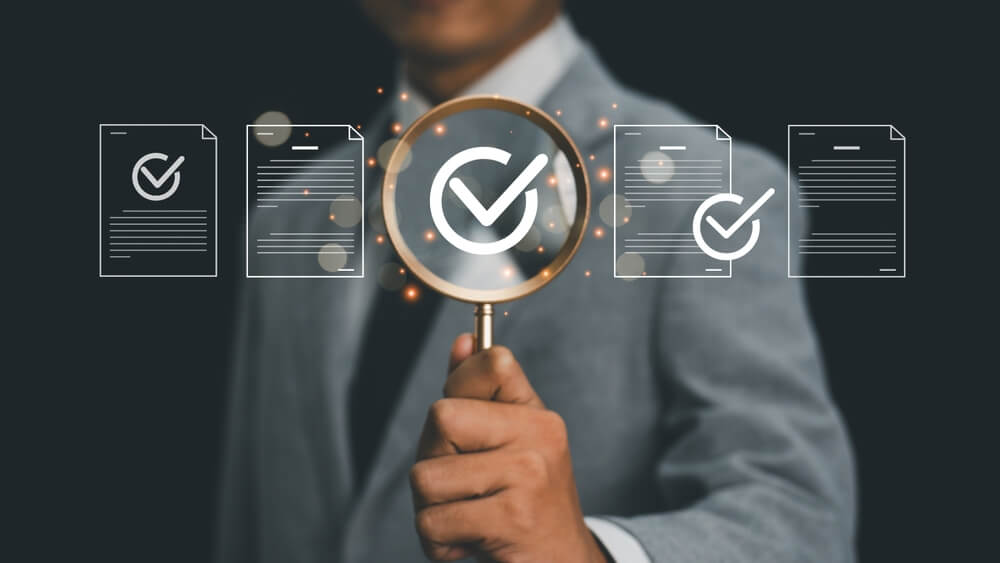ビジネスでは、多くの人とコミュニケーションをとりながら、協力しあい業務を進めていきます。時には議論や交渉を行い、双方が納得する答えを出さなければならないこともあるでしょう。相手の気持ちを尊重しつつ、自分の意見をきちんと表明することは、一見すると相反するようにも見え、難しさを感じるかもしれません。そこで有用なのが「アサーショントレーニング」です。今回は、職場でアサーショントレーニングを行うメリットや具体的な実践方法などについて詳しく解説します。
目次
アサーショントレーニングとは
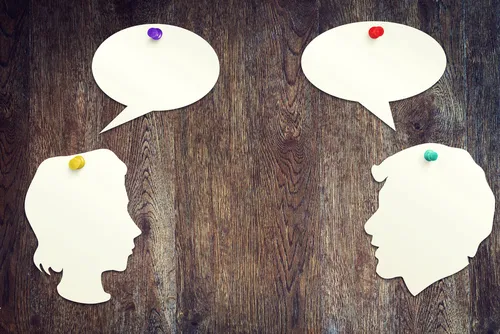
はじめに、職場における「アサーション」の意味をチェックしたうえで、アサーショントレーニングとは何か、なぜビジネスの分野で注目が寄せられているのかについて明らかにしていきます。
アサーショントレーニングとは
アサーションとは、「相手の考え方や価値観を受け入れ、尊重しながらも、自分の意見を率直に伝えるコミュニケーションスキル」です。アサーショントレーニングは、このスキルの向上を目的としたもので、適切な自己主張ができるよう、アサーションの考え方やコミュニケーションの方法について学びます。
アサーションについては、以下の記事でも詳しく紹介しています。
アサーションが注目される背景
ビジネスの分野でアサーションに関心が寄せられている背景の一つに、ダイバーシティの進展があります。組織に集まる多様な人材が、それぞれの強みを発揮できる風土の醸成が求められているためです。意見の対立を避けながら、協力して仕事を進めていくために、アサーションのスキルは重要といえます。
また、リモートワークの浸透で対面でのコミュニケーションが減少し、チャットやメールなどを用いたやり取りが増加したことも一因です。言葉に込められた意図やニュアンスを汲み取ることが難しくなる中では、認識の食い違いや誤解を減らすための相互理解が欠かせません。
さらに、ハラスメントが起きにくく、従業員がいきいきと働ける環境づくりという観点でも、円滑で建設的なコミュニケーションを図るアサーションは、その基盤をつくるうえで大きな役割を果たすといえます。
アサーショントレーニングで理解しておきたい自己表現の4つの型

アサーションでは、一人ひとりのコミュニケーションタイプ(自己表現の方法)を、以下の4つに分類しています。トレーニングを行う前に、自分がどのようなコミュニケーションを取っているのか、傾向を確認してみましょう。
アグレッシブ:一方的な主張を押し付けがちな攻撃的タイプ
アグレッシブとは、一方的に自分の意見を主張し、押し付けるタイプです。他者への配慮や理解を示す様子がなく、時に攻撃的な言葉を使い、相手よりも優位な立場につこうとします。自分の意見をきちんと主張できる点は評価できますが、他者の言葉に耳を貸さず、意見を受け入れようとしないため、衝突や軋轢が生じやすく、チームや組織にネガティブな影響を与える可能性があります。
ノンアサーティブ:自己主張が苦手な非主張的タイプ
ノンアサーティブとは、自己主張が苦手で、意見や感情をうまく表現できず、率直な意見を伝えられなかったり、相手に同調したりするタイプです。その背景には「嫌われたくない」「自分の意見を否定されたくない」といった思いがある場合も多く、周囲とトラブルになることは少ないですが、自分の意見を曲げ、我慢して相手に合わせているケースもあります。そのため、良好な関係を築いているように見えて、本人は不満を溜め込んでいることも少なくありません。また、相手の意見に従っているため、本心がわかりにくい、責任感が薄いといった傾向がみられます。
パッシブアグレッシブ:非主張的ながらも内面に攻撃的な意思を持つタイプ
パッシブアグレッシブとは、表面上は相手の意見を受け入れる姿勢を見せつつも、内面では攻撃的な意思を持ち間接的に攻撃するタイプです。アグレッシブタイプのように攻撃的な言葉を使ったり、怒りの感情をあらわにしたりすることはありませんが、否定的で消極的な態度によって不満を表現し、相手をコントロールしようとします。例えば、ため息をつく、不機嫌な態度を見せる、陰口を言う、故意に仕事を遅く進めるなどの行動が挙げられます。
アサーティブ:自分も相手も尊重できるバランスタイプ
アサーティブとは、他者と自分どちらの気持ちも尊重し、かつ主張もきちんとできるバランスタイプです。相手への配慮を欠かさず、そのうえで、その場に応じた建設的なコミュニケーションによって自分の意見を明確に伝えられるため、周囲も自分もストレスが少ないのが特徴です。4つのタイプの中では、アサーティブタイプが最も理想的なコミュニケーションのあり方といえます。
アサーショントレーニングを行うメリット

アサーショントレーニングを通してアサーションを身につけることは、従業員一人ひとりにとっても、職場や組織にとってもさまざまなメリットをもたらします。
<アサーショントレーニングを行うメリット>
- 良好な人間関係・信頼関係の構築
- ハラスメント防止・風通しの良い職場の実現
- ストレスの軽減・メンタルヘルス対策
- 業務の効率化・生産性の向上
良好な人間関係・信頼関係の構築
アサーショントレーニングを行い、建設的で円満なコミュニケーションがなされれば、良好な人間関係の構築につながります。他者の意見や価値観を尊重し、適切な言葉を選びながら意思疎通を図るため、相手に不快な気持ちを抱かせにくいでしょう。開かれたコミュニケーションができる環境は、相互理解と信頼関係を深める基盤となります。
ハラスメント防止・風通しの良い職場の実現
ハラスメントが起きやすい職場は、「否定を恐れて意見を言えない」「わからないことがあっても聞けない」「感情に任せた一方的な発言をする人がいる」など、心理的安全性が低い環境といわれています。アグレッシブタイプのような攻撃的な主張は、場合によってはハラスメントに該当する可能性もあるため、アサーションによって適切な自己主張の方法を学ぶことは、職場のハラスメント防止にもつながります。
また、アサーショントレーニングを通じて、適切なコミュニケーションの方法が身につくと、心理的安全性の高いチーム、組織を実現することが可能です。誰もが自分の意見を真っ向から否定されず、率直に述べられる環境では、ポジティブな対話が生まれ、チームや組織にも協力的な雰囲気が醸成されるでしょう。
風通しの良い職場づくりについては、以下の記事でも詳しく紹介しています。
ストレスの軽減・メンタルヘルス対策
アサーショントレーニングは、コミュニケーションを行う中で感じるストレスの軽減にもつながります。例えば、周囲に合わせがちで自己主張が苦手な人の場合、忙しい中で業務を任されても断れず、「自分ばかり負担が大きい」と不満を溜め込んでいることもあります。アサーションを活用すると、自分の要望を伝えながらも、相手に配慮することで健全なコミュニケーションができるため、強いストレスを感じにくくなるでしょう。また、職場の人間関係を端緒とするメンタル不調の予防という役割もあり、メンタルヘルス対策としても有効です。
アサーショントレーニング方法

続いては、職場でアサーショントレーニングを行う方法と、実践アイディアについてご紹介します。
トレーニング①DESC法
DESC(デスク)法は、相手にわかりやすく意見や気持ちを伝えるためのフレームワークです。アサーションのプロセスを状況、気持ち、解決、提案という4つのステップに分け、伝え方を整理しましょう。DESC法を意識してコミュニケーションを取ることで、アサーティブな意思表示が身につきます。DESC法では、以下の4つの順番に主張を伝えてコミュニケーションを取ります。
| ①Describe(描写する) | 客観的な視点で状況を捉える |
| ②Explain(表現する) | 自分または相手の気持ちを主観的に説明する |
| ③Suggest(提案する) | 自分も相手にも寄り添った解決策を提案する |
| ④Choose(選択する) | 提案を受け入れられた時とそうでなかった時にどうするか、自分の行動を選択する |
具体的な例題は次の章で紹介します。
実践方法②I(アイ)メッセージ
自分を主語にして伝える「I(アイ)メッセージ」を心がけることも、アサーショントレーニングとして有効です。例えば、「あなた」を主語とする「YOU(ユー)メッセージ」は、やや攻撃的で、冷たい印象を受けることもあります。一方で「(あなたが)急いで対応して欲しい」を、「急ぎで対応してもらえると(私は)助かります」とIメッセージに言い換えると、自分の気持ちをわかりやすく伝えることができ、かつ、相手の行動を直接否定(批判)しないやわらかいニュアンスになるため、配慮もみえる表現になります。
アサーショントレーニングは、実践して身につけていくことが大切です。従業員にアサーションのスキルを身につけてもらうには、日頃の意識はもちろん、研修やワークショップの実施が効果的です。
アドバンテッジリスクマネメントでは、対人コミュニケーションの基礎能力とされるEQ(感情マネジメント力)向上を目的とした研修を提供しています。アサーションはEQを構成するうちの一つ(対人関係知性)に分類され、アサーション能力の向上にも役立ちます。
アサーショントレーニングの例題

ここからは、アサーショントレーニングの例題をご紹介します。
DESC法を用いたアサーション
業務のとある場面を想定し、DESC法を用いた方法でアサーションについて学びましょう。
【例題】
上司から、急ぎの資料作成を頼まれたが、他の仕事もたまっていて引き受けることが難しいので、断りたい。どのように伝えますか?
この場面において、DESC法を活用した回答例は以下です。
【DESC法を用いた回答例】
①Describe(描写する):
明日が締め切りの仕事がいくつかあります。
②Explain(表現する):
できればお力になりたかったのですが、時間をとれず、今回は難しそうです。申し訳ございません。
③Suggest(提案する):
今担当している業務の締め切りを調整していただければ対応できそうですが、いかがでしょうか。
④Choose(選択する):
【OKの場合】ありがとうございます。ではこちらの資料作成を優先して進めますね。
【NGの場合】では、簡単なものならAさんに任せて、私が作成のサポートに入りましょうか。
自己表現タイプ別のロールプレイング
店員役、お客さん役のペアを組み、以下の状況でそれぞれの自己表現タイプのロールプレイングを通じて理解を深めましょう。
【状況】
喫茶店でコーヒーを注文。店員が運んできたコーヒーを、お客さんの洋服にこぼしてしまいました。
【ロールプレイング内容】
①お客さん役は、「洋服が汚れてしまって困った」ことを攻撃的に表現します。(アグレッシブ)
②店員役に、攻撃的に表現された際の気持ちを尋ねます。お客さん役にも演じた感想を尋ねます。
③つぎにノンアサーティブ、パッシブアグレッシブ、アサーティブの自己表現でそれぞれロールプレイングを行います。
参考:厚生労働省「ゲートキーパー養成研修用テキスト第二版」P325
【タイプ別の反応例】
- アグレッシブ:「洋服が汚れてしまったじゃないか」と怒鳴る
- ノンアサーティブ:「お気に入りの服だったのに」と思いながら「大丈夫です」と言う
- パッシブアグレッシブ:本当は不満だが「大丈夫です」と言い、あとで喫茶店の悪い口コミをネットに書き込む
- アサーティブ:「バランスが悪かったようなので仕方ないですよ」と相手に理解を示しつつ、「その代わりといってはなんですが、クリーニング代を一部負担いただくご相談はできますか?」と交渉する
アサーショントレーニングを成功させるためのポイント

アサーションによるコミュニケーションでは、どのような心がけが求められるのでしょうか。アサーショントレーニングの実践時に意識したいポイントをチェックしていきましょう。
アサーション権について知る
まずは、誰もがアサーション権を持っていることを理解しましょう。アサーション権とは、平たく言えば「意見を主張してよい権利」のことです。「断ったら申し訳ない」「忙しい人に頼みごとをしづらい」と考えるかもしれませんが、人は「頼みごとをしてもよい」「断ってもよい」のどちらの権利も持っています。どちらの権利も尊重し、双方にとってよりよい形になるよう、建設的なコミュニケーションを通して歩み寄ることが重要です。
自分の気持ちを把握する
自分が今どんな気持ちであり、どんな意見を持っているのかを明確に把握することが、アサーションの第一歩です。例えばトラブルに巻き込まれてネガティブな感情を持ったら、「こんなことを思ってはいけない」と気持ちに蓋をするのではなく、「困った」「面倒だな」という感情を否定せず、ありのままを一旦受け入れ、客観的に感情を整理しましょう。
なぜ困った、面倒だと思ったのかをアウトプットしてみると、その理由に気づけることもあります。「納期が迫っている仕事があるのに、このままでは間に合わなさそうで困っている」と、具体的に整理することで、不安や怒りに振り回されることが減り、前向きな対話が可能となります。
非言語コミュニケーションも意識する
「あなたの提案がいいと思う」と口にしていても、不機嫌そうな表情をしていたり、目を合わせなかったりすると、相手は「本当はそう思っていないのかもしれない」と捉えてしまう可能性もあります。言葉だけでなく、表情や身振り手振り、声のトーンなどの非言語コミュニケーションでも、相手への配慮が感じられるよう意識しましょう。
異なる意見も受け入れる
もし、自分と相手の意見が異なっていても、一旦肯定し、受け入れることが大切です。「いや」「でも」とすぐに反対するのではなく、「なるほど」「そうですね」と、相手の気持ちを尊重し、受け止める姿勢を見せたうえで、「私はこのように思います」と伝えます。相手は「自分の意見を聞いてくれた」と感じるため、その後に反論を述べても、気持ちよくコミュニケーションを続けられます。
継続してトレーニングを実施する
アサーショントレーニングは、研修を実施するだけでなく、日々の仕事やコミュニケーションでの実践を重ねることで身についていくものです。研修やワークショップを定期的に行うほか、1on1やフィードバックの中でアサーションができているか確認する機会を設けたり、チームミーティングなどでもコミュニケーションについて振り返りを行ったりすることが重要です。
アサーションが活用できるシーンの例

アサーションは、日頃のコミュニケーションはもちろん、人事評価面談や、あるいは採用活動などの場面で活用できます。ネガティブなフィードバックや伝えにくい内容であっても、相手の気持ちに寄り添いながら、適切な言葉を選んで改善点を伝えることで、部下は素直に意見を受け止められるでしょう。
また、採用活動の場では、企業側の担当者がアサーションを意識してやり取りを行うと、応募者と対等かつ良好な関係を築け、相互理解が深まります。
前向きなコミュニケーションが生まれる職場へ

アサーショントレーニングを通してコミュニケーションの質が高まると、誰もが対等な立場で建設的に対話できる、心理的安全性の高い職場環境の実現につながります。アサーションのスキルを身につけていくためには、DESC法などを用いて思考の整理を行うとともに、実務を想定したロールプレイングなどで一連のプロセスを実際に体験することが大切です。実務においても、自分のコミュニケーションを振り返れる機会があると、アサーションへの理解がより深まります。アサーションによるコミュニケーションを浸透させ、前向きなコミュニケーションが生まれる職場を目指しましょう。